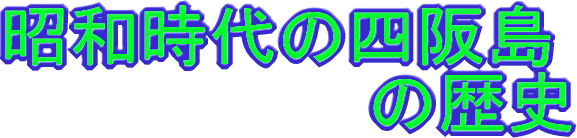
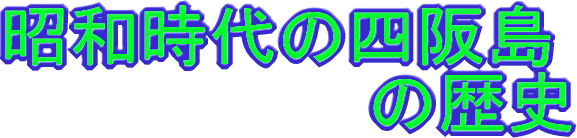
| 昭和元年(1926) | 第一、第三傾斜道完成 | |
| 昭和 2年(1927) | 1月 | 四阪島改善会発表会式挙行 |
| 木津川丸 今治−大阪間航路に変更 | ||
| 第一四阪丸 尾道−新居浜間 | ||
| 第二四阪丸 新居浜−四阪−今治 | ||
| 11月 | 微粉炭工場完成、全鎔鉱炉を微粉炭吹とす | |
| 鎔鉱炉約50名整理 | ||
| 昭和 3年(1928) | 2月 | 即設電気収塵設備を改修し、転炉排煙全部を処理することとし操業開始 |
| 8月 | 暴風雨により船頭町の大半流出 | |
| 9月 | 湿式製錬試験設備完成し、試験操業開始 | |
| 10月 | ペテルゼン式硫酸工場建設に着手 | |
| 昭和 4年(1929) | 7月 | ペテルゼン式硫酸工場第一期工事(焼結炉排ガス処理)完成操業開始、竣工式挙行(9月) |
| 8月 | 新居浜−四阪島間、新ケーブル敷設完成送電開始 | |
| 昭和 5年(1930) | 1月 | 鎔飠式は明治以来中断していたが、本年より毎年行う |
| 5月 | ペテルゼン式硫酸工場第二期工事(転炉排ガス処理)完成操業開始 | |
| 5月 | 焼結炉一基増設(4号炉)操業開始 | |
| 北浦桟橋完成し回漕店移転す(現在地) | ||
| 7月 | 第8回煙害協議会(松山にて) | |
| 昭和 6年(1931) | 2月 | 火力発電所廃止 |
| 5月 | 西巽販売所(現在社員食堂)を拡張し、日暮販売所を統合 | |
| 8月 | 硫酸工場に於て硫酸補給用にアンモニア酸化器を設備し、操業を開始 | |
| 昭和 7年(1932) | 9月 | 硫酸工場拡張起業完成、生産能力360トン/日 |
| 昭和 8年(1933) | 5月 | 焼結炉一基(5号炉)増設 |
| 5月 | 硫酸工場増産起業施行 | |
| 7月 | 鎔鉱排ガスをアンモニアによる中和試験開始 | |
| 集落消火設備増強(測候所北側に丸タンク設置) | ||
| 昭和 9年(1934) | 2月 | 焼結炉一基(6号炉)増設 |
| 3月 | 生鉱吹廃止し純焼鉱吹に移行 | |
| 昭和10年(1935) | 御住崎に水平引込式起重機一基新設、直接汽船の物を陸揚 | |
| 昭和11年(1936) | 羽口微粉炭装入をやめ羽口調整は塊炭とする。 | |
| 四阪島行曳船全廃し、機械船輸送となる。 | ||
| 明神島海水浴場開設(これより毎夏) | ||
| 日暮浴場を西巽頂上に移転 焼結炉鉱煙全部硫酸工場に導入 | ||
| 昭和12年(1937) | 4月 | 桜谷公園開設(美ノ上谷、桜数十本) |
| 12尺準更衣室及び食堂新築落成 | ||
| 中和工場第一期工事着工 | ||
| 蓄電池式装入電車をトロリー式機関車変更 | ||
| 粗銅冷却装置を新設 | ||
| 5月 | 修理工場改築(明治36年以来のもの) | |
| 7月 | 別邸日本間増築、客室、浴槽移転 | |
| 新居浜−四阪島間の被曳船廃止 | ||
| 11月 | 尚志寮新築 | |
| 12月 | 中央倶楽部(2階)及び浴槽(1階)新築落成 | |
| 昭和13年(1938) | 5月 | 亜鉛製錬の試験工場完成、試験始める |
| アンチモニー製錬の研究始まる | ||
| からみより製鉄の研究始まる | ||
| 純硫酸製造装置すすめる | ||
| 御住崎煙突取こわし(ニッケル工場建設のため) | ||
| 7月 | 中和工場設備完成、試験操業開始 | |
| 昭和14年(1939) | 4月 | 住友四阪島製錬所技能者養成所設立 |
| 中和寮(職員合宿所)新築 | ||
| 青年学校建家新築(事務所東側) | ||
| 7月 | 中和工場完成、式典挙行(10月)煙害問題完全に解決 | |
| 8月 | ニッケル鎔錬工場完成試験操業開始 | |
| 煙害を理由とする賠償金及び農林業奨励寄付金は昭和14年までの累計金額合計約730万円巨額に達す四阪島煙害問題解決 | ||
| 第11回煙害協議会において協定書調印 | ||
| 御住崎より新設の小型転炉廃止 塩基性転炉1基増築 | ||
| 昭和15年(1940) | 5月 | 事務所焼失 |
| 昭和16年(1941) | 5月 | 御住崎にNO2ラッフィンクレーン設置 |
| 神社移転造営落成(現在地)遷座祭を執行する | ||
| 5月 | 事務所新築落成式挙行(現在地) | |
| 6月 | 鉱滓綿製造試験に着手 | |
| 昭和17年(1942) | 中和工場液化亜硫酸製造開始 | |
| 新居浜−四阪島間海底ケーブル敷設(第三次)60サイクル1万1000V | ||
| 昭和18年(1943) | 12月 | 有信寮焼失 瓦斯 火車新設 3月25日鎔鉱第一号炉にてNI鉱石処理11月19日NI製錬中止 |
| 昭和19年(1944) | 酸素工場新設操業開始(35年廃止) | |
| CFコットルの煙灰流送用タンク新設 | ||
| 昭和20年(1945) | 電気製塩素操業(25年廃止)HFの瓦断点火車休止 | |
| 昭和21年(1946) | 1月 | 銅鎔鉱炉火入れ(戦後全国で最初) |
| 石灰製造(ニッケル鎔鉱炉を石灰石焼成炉とする)22年3月中止 梶島開こん農耕 | ||
| ニッケル用10段焙焼炉(CuBFの南側)で銅精鉱の焙焼開始 | ||
| 3月 | 有信寮再建 | |
| 昭和22年(1947) | 労働組合33日間の長期ストライキ(鎔鉱炉の火消ゆ) | |
| 昭和23年(1948) | 測候所閉鎖 故銅単独処理試験始む 操業始める | |
| 昭和24年(1949) | ニッケル8段焙焼炉をCuBF南側に移設し、銅精鉱の焙焼開始 | |
| 昭和25年(1950) | 新ペテルゼン法(硫酸)技術導入 | |
| 硫酸亜鉛及インゴット鉛製造開始(31年廃止) | ||
| CF 水砕装置設置 | ||
| 昭和26年(1951) | 半生鉱吹試験開始 | |
| 硫酸工場の機械修理及分析室焼失 | ||
| 4月 | 町立保育園開設 | |
| 昭和27年(1952) | 5月 | ニッケル鎔煉工場再開、竣工式挙行 |
| 越智郡宮窪村から宮窪町となる | ||
| 5月 | 生鉱吹起業のため、焙焼炉2炉共休止 | |
| 昭和28年(1953) | 生鉱吹切替工事 生鉱吹開始 | |
| 昭和29年(1954) | 11月 | 銅焙錬、生鉱吹製錬法に全面転換、全排ガス硫酸工場へ (焼結工場、中和工場廃止) |
| 12号、15号台風による工場、社宅共被害甚大 | ||
| 昭和30年(1955) | 2月 | 各浴場及更衣室を12尺準に統合 |
| 昭和31年(1956) | 硫酸工場蛇管クーラーからイリゲーションクーラー新設 | |
| 10月 | 学校創立20周年記念式典挙行 | |
| 看護婦寮下広場に社宅新築 PS転炉起業着手 | ||
| 昭和32年(1957) | 硫酸工場、亀ヶ浦へウルトラフィルター新設 | |
| 海底ケーブル(22kv用)布設 回漕店桟橋取替 | ||
| 5月 | 学校に水族館開館 | |
| 昭和33年(1958) | 3月 | PS式転炉完成 |
| 酸化ニッケル生産開始 | ||
| 昭和34年(1959) | 銅鎔鉱炉 の水砕設備完成、水砕 の製造開始 | |
| 9月 | 四阪生協発足(配給所より引継) | |
| 昭和35年(1960) | ニッケル鎔練が鉱と精鉱による混合吹開始 | |
| 昭和36年(1961) | 硫酸工場新ペテルゼン式に設備改造完成 | |
| 東海岸へ淡水500tタンク新設 | ||
| 埋地アパート新築完成 | ||
| 4月 | 学校公立移管(宮窪町立となる) | |
| 昭和37年(1962) | ペレタイザー設置 | |
| 昭和38年(1963) | 2月 | ベスレヘム銅精鉱の第一船入船 |
| Ni増産のために混合吹とが鉱単独吹に熱風炉試験実施 | ||
| 昭和39年(1964) | 銅製錬増強起業 | |
| ニッケル製錬熱風吹込設備 | ||
| 昭和40年(1965) | 2月 | ケミコ式濃硫酸工場新設完成、竣工式挙行 |
| 銅製錬日量300トンから380トン熔解に増強 | ||
| 町立火葬場新設(勝浦之避病舎跡) | ||
| 昭和41年(1966) | ニッケル鎔鉱炉拡張 | |
| 巽アパート新築完成 | ||
| 昭和42年(1967) | 銅製錬日量380トンから500トン精鉱熔解に増強 | |
| 強風重油吹 | ||
| 昭和43年(1968) | 銅製錬日量380トン精鉱熔解に増強 | |
| ニッケル増産起業施行 | ||
| 昭和44年(1969) | 頂上集落、下段及中段社宅新築(2階建) | |
| 昭和45年(1970) | 町立公民館開設(美の上クラブ) | |
| 昭和46年(1971) | 9月 | 銅製錬精鉱210トン/日に減産後9月吹卸し |
| 12月 | ニッケル精鉱生吹完成(東工場で12月より操業) | |
| 頂上集落上段社宅新築(2階建) | ||
| 昭和47年(1972) | 11月 | 銅製錬1年1ヶ月ぶりに再開(西工場で11月9日火入れ) |
| 昭和48年(1973) | 10月 | 町立プール開設(山頂) |
| 昭和49年(1974) | 16号台風の直撃を受けて淡水揚設備倒壊 | |
| 昭和50年(1975) | 5月 | ニッケル製錬停止、24年間に亘るニッケル鎔鉱炉の火は消えた |
| 昭和51年(1976) | 2月 | 銅滓、白ペレット処理製錬開始 |
| 4月 | C式濃硫酸製造廃止 | |
| 9月 | 台風17号連日の大雨により各所崩壊、被害甚大 | |
| 11月 | 銅精鉱による製錬休止、7年間に亘る銅鎔鉱炉の火は消えた | |
| 昭和52年(1977) | 4月 | 通勤体制に移行 |
| 10月 | 酸化亜鉛製造設備完成、操業始まる | |
| 昭和53年(1978) | 2月 | 救急艇(ひぐらし)就航 |
| 7月 | 酸化亜鉛還元キルンコーチングカッター(削り長さ5m) 設置し、操業の効率化がはかられる | |
| 10月 | 銅滓、白ベレ処理製錬停止 | |
| 昭和54年(1979) | 1月 | 明神島の松枯れ対策実施(ヘリコプターによる薬剤散布) |
| 7月 | 酸化亜鉛還元キルンのコーチングカッター改造(削り範囲5mより10mに延長) | |
| 昭和55年(1980) | 3月 | 新船みのしま(客船兼淡水タンカー |
| 11月 | 酸化亜鉛還元キルン操業変更(原料を内装法より外装法へ)し、コストの大巾低減に寄与した | |
| 昭和56年(1981) | 5月 | 老朽化社宅解体開始(美ノ浦社宅より実施) |
| 昭和57年(1982) | 9月 | 台風19号により新居浜〜四阪間の海底ケーブルに大型船の錨が掛かり、全線が断線 |
| 12月 | 酸化亜鉛2段キルン法パイロット試験実施 | |
| 美の浦部落3段目解体 | ||
| 昭和58年(1983) | 9月 | OB会発会式(一島一家と呼称) |
| 10月 | 酸化亜鉛還元キルン直火バーナー試験実施 | |
| 昭和59年(1984) | 12月 | 四阪島工場操業開始以来初めて完全無災害達成 |
| 9月4日 | 明見谷集落焼却 21戸 | |
| 10月26日 | 吉備浦集落焼却 56戸 | |
| 昭和60年(1985) | 7月12日 | 吉備峠集落社宅焼却147戸 |
| 8月6日 | 西日暮集落社宅焼却157戸 但し山中に近い14戸残す | |
| 8月6日 | 巽浦集落社宅焼却11戸 | |
| 8月6日 | 養正寮解体 | |
| 年間完全無災害 所長表彰(2年連続) | ||
| 昭和61年(1986) | 4月 | 四阪工場無医化となる |
| 団鉱生産中止 | ||
| 年間完全無災害 所長表彰(3年連続) | ||
| 長期完全無災害 社長表彰(120万時間) | ||
| 4月24日 | 日暮集落社宅焼却17戸 | |
| 日暮集落社宅解体4戸 | ||
| 7月8日 | 美の浦集落社宅焼却63戸及び尚志寮 アパート残す | |
| 8月22日 | 糯ヶ岡、東巽集落社宅焼却167戸及び有信寮 | |
| 8月28日 | 北浦集落社宅焼却64戸 | |
| 昭和62年(1987) | 2月 | ペテルゼン式硫酸工場休止 |
| 2月 | ニッケル焙焼工場休止 | |
| 2号海底ケーブル地絡事故 | ||
| 5月 | 完全通勤体制 |